阿賀野市の食事処 結桜(ゆいざくら) <五頭山麓の四季>
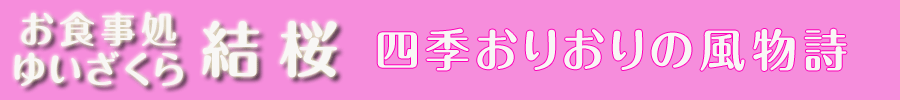 |
| |
| 店名の由来となった満開の結桜(令和3年4月7日撮影) 一本に樹に濃い赤紫の花と白い花が混在していました。今年の結桜の満開もソメイヨシノより5日程遅れていました。   |
| 結桜(写真左下=令和2年4月16日撮影)とソメイヨシノ(写真右下=令和2年4月8日撮影) 結桜は、ヤマザクラのように葉が広がってから開花します。開花はソメイヨシノより5日程遅れます。     レストラン結桜近くの五頭山麓には、野生の山葵(ワサビ)が自生しています。 山葵はアブラナ科の多年草で、早春に渓流脇の雪が解けると青々とした葉を広げ4弁の白い花を咲かせます。 アブラナ科であるワサビの花も、成長するとその姿は「菜の花」そのものです。 長野県や静岡県で有名なワサビは、野生種を品種改良したものだそうです。   下の写真はコマツナの花(左)とダイコンの花(右)-4月中旬撮影 どちらも山葵と同じアブラナ科に属します。アブラナ科の特徴は、いわゆる「菜の花」を咲かせる事です。 春の七草のナズナ(アブラナ科)はペンペン草とも呼ばれていますが、やはり花の姿は小さな「菜の花です」。 新潟県阿賀野市では、春の七草と言えどもペンペン草を食べたと言う話しは聞いたことがありません。 広い平野がある越後の国では、保存食としたキャベツ(甘藍)や白菜(いずれもアブラナ科)に不自由しなかったためと 考えられます。   下の写真はショウジョウバカマ(猩々袴)とミズバショウ(水芭蕉)-4月初旬撮影 五頭連峰やその西側の笹神丘陵の裾野には湿地が点在しています。猩々袴は湿地に隣接する日陰がちな林に 自生しており、他の植物がまだ成長しきっていないので直ぐに見つかります。広辞苑などによれば、「猩々」とは、 能で緋色の袴を着けている酒好きな精霊でめでたい存在だそうです。   下の写真は、いこいの森の躑躅(ツツジ)とクロアゲハ  |
| 阿賀野市五頭連峰の西側に並立する笹神丘陵(参考=WebGuide阿賀野)の山裾に小さな湿地が点在します。 そのような湿地には、日本最小のトンボであるハッチョウトンボが生息しています。 このハッチョウトンボは、拡大写真では普通の赤トンボに見えますが、実は全長2cm程しかありません。 ここ40年程で、山裾の湿地が陸地化して随分減ってしまいましたが、それでも所々でこのトンボを見つける事ができます。   五頭連峰周囲の湿地に自生する、ラン科のサギソウ(鷺草-写真左)とモウセンゴケ(毛氈苔-写真右) サギソウは、ラン科の中でも最も可憐な姿をしています。 モウセンゴケは「苔」と言う名前は付いていますが、れっきとした裸子植物です。食虫植物ですので、 この写真の用に昆虫が捕まってしまいます。   笹神丘陵には、江戸時代に溝口藩(新発田藩)によって造られた潅漑用の溜め池がいくつかあります。 その中の一つ「じゅんさい池」ではじゅんさいの栽培が行われています。ジュンサイはスイレンの仲間の多年草で、 『古事記』や『万葉集』にも記載されるほど古くから高級食材として珍重されてきました。 水面下で成長する新芽はゼリー状の膜で覆われており、その喉ごしがツルッとして夏の到来を予感させます。   写真左は、いこいの森の大荒川。写真右は、カジカガエル。 いこいの森では、森林浴をしながらの散策やキャンプ/バーベキューが最高です。石窯も設置してありました。 大荒川では可憐なカジカ蛙の鳴き声が響いていました。鳴くのはオスだけだそうです。 「いこいの森」はこちらをどうぞ     左の写真はバイカモ(梅花藻) 右の写真はガマ(蒲) バイカモは、梅の花に似ていることが名前の由来です。水温が25℃以上では生育できないそうです。土水路が減ってきた 阿賀野市でも大変珍しい多年生の沈水植物ですが、種子繁殖の他、切れ藻でも繁殖するようです。 日本神話で有名な「因幡の白兎」が治療に使った”水門の蒲”もこのガマと考えられているそうです。 ガマは湖沼や川の岸辺に生育する多年生の植物です。 新潟県には蒲原郡という地名がありますが、その「蒲原」はガマが生い茂っていた事に由来します。   |
| ヒガンバナの花(写真左)と花茎(写真右) ヒガンバナは、その名の通り秋のお彼岸の頃に咲き出します。球根から芽が出始めたら、ぐんぐんと成長します。 一週間ほどで50-60cmまで伸びてあっという間に咲き出します。但し、天候が不順な年は二週間ほど要します。 別名は曼珠沙華(まんじゅしゃげ)。サンスクリット語の音写との事で仏教に関係があるようです。 このヒガンバナは、生物学的には三倍体のため種子ができないと言われています。しかし、球根を移植したわけでも ないのに時々全く心当たりのない場所でヒガンバナが咲いている事があります。その理由は、未だ解明されていない ようですが、一月ほど早咲きで外見に違いのない二倍体のコヒガンバナという種類もあるそうです。   下の写真は、いこいの森に自生していた柿。ヤマガキでしょうか? 枠の中は八珍柿(はっちんかき)。命名したのは親鸞聖人と言われています。 承元の法難で35歳の時に越後に流刑となった親鸞聖人が「越後七不思議」の次に珍しい物だという事だそうですす。 京都生まれの親鸞聖人にとっては、種なしの渋柿が珍しかったようです。 この八珍柿は、平核無(ヒラタネナシ)とも言われ、渋を抜いた醂柿(さわしがき)にして食します。 新潟県阿賀野市でも「おけさ柿」として産地化しています。  下の写真は、秋のいこいの森(当店から新発田市の方向に4km弱) いこいの森は、五頭連峰から流れ出る大荒川の土石流によって形成された扇状地の左岸に位置します。 この土石流は、豊臣秀吉(木下藤吉郎)誕生の前年1536年に発生したものと推定されています。 土石流扇状地である証拠に、園地には巨石がゴロゴロしています。   |
| オオハクチョウ(写真左)とコハクチョウ(写真右) 冬の阿賀野市と言えば、瓢湖の白鳥が有名です。良く見かける白鳥はオオハクチョウとコハクチョウの二種。 パッと見て区別するには、体の大きさや首の長さでは難しいので嘴(くちばし)の黄色で区別します。 鼻孔の先まで黄色くなっているのが、左のオオハクチョウです。   写真左下はオオヒシクイ(大菱食)と白い額のマガン(真雁)。右下の写真はシジュウカラガン(四十雀雁)の群れ 左下の写真は阿賀野市熊堂地区で撮影した写真です。右下の写真は福島潟近くの田んぼで撮影しました。 その名の通り、オオヒシクイは菱(ヒシ)が大好きなのでしょうか?その昔、忍者が撒き菱(まきびし)に 使ったというヒシは、阿賀野市の池や排水路でも時々見かけます。 シジュウカラガンは、時々福島潟近辺で見かけます。四十雀のように頬が白いのが特徴です。   写真左のパンダの様な水鳥はミコアイサのオス(後ろはオナガガモのメス)、右の写真はオオバン 名前の語源/由来は、どちらもネットで散見されますが少々疑問もあります。 ミコアイサは潜水が得意なカモの仲間で、瓢湖ではかなり珍しい種類です。 額と嘴が白いオオバン。この鳥は、鴨ではなく鶴の遠縁です。沖縄のヤンバルクイナに近い種だそうです。   |
| 新潟県阿賀野市五頭温泉郷うららの森のレストラン 結桜(ゆいざくら) TEL250-61-3511 先頭へジャンプ |